新医療費体系を巡る国会審議を第19回国会衆議院厚生委員会議録第60号(昭和29年10月1日)でみてみる。(草葉隆圓厚生大臣) この新医療費体系の意図いたしますところは、医療に対して適正なる報酬を支払う方式を確立いたすことでありまして、医師、歯科医師、薬剤師の技術に対しましては、その専門的技術に対するものとして、適正なる報酬を支払いますとともに、物に対しては物に対するものとしての対価を支払う原則をとるものであります。 (草葉隆圓厚生大臣) 今回の新医療費体系の骨子をなしますものは、第一には医師、歯科医師の診察に対しましては適正なる診察料を支払うことといたし、その点数は実態調査によるものとすること、第二には薬治料の内容を分析いたしまして、調剤料と薬品原価を薬剤師に支払い、従来医師が薬治料の中に含めて得ておりました診察料的部分は、これを医師、歯科医師の診察料に含めることといたしました。第三には、注射料といたしましては、従来注射で得ておりました報酬のうちから、技術料と原価を残しまして、他は診察料に含めることといたしました。第四は、処置料の四点以下は診察料に含めることといたしました。第五に歯科の補綴につきましては、従来補綴料とされていた報酬のうちから技術料と物の対価を残しまして、その他は診察料に含めることにいたした等でございます。 (曽田長宗医務局長) 歯科ではそもそも診察だけというというような行為が割合に少くなっておりますので、このプラス、マイナスいずれにいたしましても大きな数字ではないのでありますが、ここでは補綴料というものが大きいプラスを示しております。いわゆる義歯、入れ歯でございます。この義歯によってプラス出ておるということで、そのほかの処置等が反面マイナスになっておるという状況であります。 (曽田長宗医務局長) それから最後に歯科の補綴料でございますが、歯科の場合にも、先ほど申し上げましたように、純粋の内科、小児科のような診察料というものは上って参らない。ごくわずかでございます。歯科においては、初診料、再診料を別建とすることは、眼科、耳鼻科で説明申し上げましたと同じような意味で、やはり好もしくない姿ではないかというふうに思われまして、歯科におきましても内科、小児科あるいは眼科、耳鼻科と同じように、同程度の診察料を支払うことにする。そしてその財源は、補綴料において大きなプラスを出しておりまして、それを診察料の方に移して行く。それで計算いたしますと、おおむね数字が合って参っておるわけであります。こういうことで大体の構想がまとまったのであります。
日本歯科医師会
富山県歯科医師会
富山市歯科医師会
新医療費体系を巡る国会審議を第19回国会衆議院厚生委員会議録第60号(昭和29年10月1日)でみてみる。
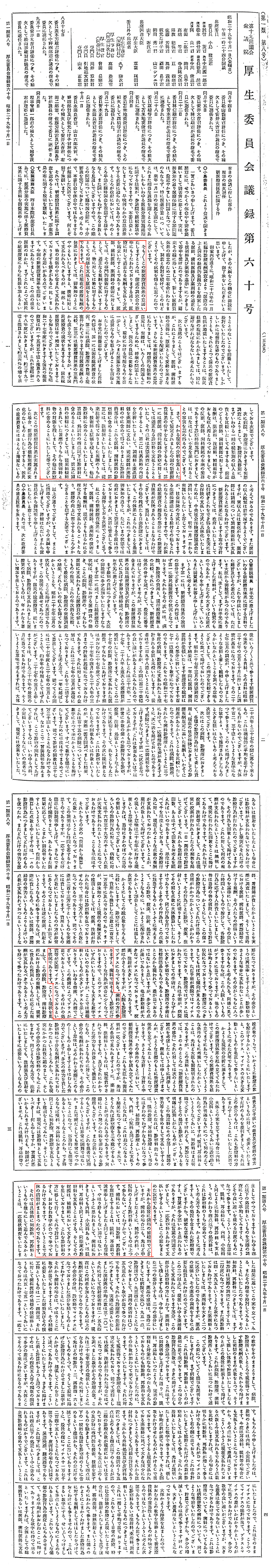
(草葉隆圓厚生大臣)
この新医療費体系の意図いたしますところは、医療に対して適正なる報酬を支払う方式を確立いたすことでありまして、医師、歯科医師、薬剤師の技術に対しましては、その専門的技術に対するものとして、適正なる報酬を支払いますとともに、物に対しては物に対するものとしての対価を支払う原則をとるものであります。
(草葉隆圓厚生大臣)
今回の新医療費体系の骨子をなしますものは、第一には医師、歯科医師の診察に対しましては適正なる診察料を支払うことといたし、その点数は実態調査によるものとすること、第二には薬治料の内容を分析いたしまして、調剤料と薬品原価を薬剤師に支払い、従来医師が薬治料の中に含めて得ておりました診察料的部分は、これを医師、歯科医師の診察料に含めることといたしました。第三には、注射料といたしましては、従来注射で得ておりました報酬のうちから、技術料と原価を残しまして、他は診察料に含めることといたしました。第四は、処置料の四点以下は診察料に含めることといたしました。第五に歯科の補綴につきましては、従来補綴料とされていた報酬のうちから技術料と物の対価を残しまして、その他は診察料に含めることにいたした等でございます。
(曽田長宗医務局長)
歯科ではそもそも診察だけというというような行為が割合に少くなっておりますので、このプラス、マイナスいずれにいたしましても大きな数字ではないのでありますが、ここでは補綴料というものが大きいプラスを示しております。いわゆる義歯、入れ歯でございます。この義歯によってプラス出ておるということで、そのほかの処置等が反面マイナスになっておるという状況であります。
(曽田長宗医務局長)
それから最後に歯科の補綴料でございますが、歯科の場合にも、先ほど申し上げましたように、純粋の内科、小児科のような診察料というものは上って参らない。ごくわずかでございます。歯科においては、初診料、再診料を別建とすることは、眼科、耳鼻科で説明申し上げましたと同じような意味で、やはり好もしくない姿ではないかというふうに思われまして、歯科におきましても内科、小児科あるいは眼科、耳鼻科と同じように、同程度の診察料を支払うことにする。そしてその財源は、補綴料において大きなプラスを出しておりまして、それを診察料の方に移して行く。それで計算いたしますと、おおむね数字が合って参っておるわけであります。こういうことで大体の構想がまとまったのであります。